初めて子猫を迎えたときは、手足を軽く噛む程度で、のんびりとした日々が続いていました。
ところが6ヶ月齢前後になってから、座っていると髪をかじり、立っていると内ももを咬む…完全に要求噛みです。痛すぎて応えるしかない場面も。
最初は戸惑いましたが、元動物看護師としての知識をもとに、噛ませない工夫や正しい遊び方を試行錯誤してきました。
しかも、乳歯と永久歯では噛む力が全く違うため、甘噛みのまま放置すると成猫になってからも困る可能性があります。
この記事では、私のリアル体験と専門知識を交えて、
- なぜ子猫は甘噛みをするのか
- 甘噛みをやめさせる具体的な方法
- 万が一のケガへの対処
を解説します。
振り回されることはあっても、本気噛みなどの問題行動に発展させず、信頼関係を築きながら、猫ちゃんとの生活を思いっきり楽しんで、猫沼にハマっちゃいましょう!
子猫の甘噛みはなぜ起こる?
遊びや狩猟本能の表れ

猫ちゃんはもともとハンター。
噛む行為自体は本能で、やめさせることはできません。
母猫や兄弟猫とじゃれ合う中で「力加減」を学びますが、早く家族と離れた場合や単独飼いの場合、十分に学べず、強く噛むことがあります。
わが家でも突然、ガブッ!痛っ!と驚くことが何度もありました。
本人は遊びのつもりでも、受ける側は痛くてたまりませんよね。
歯の生え変わりによるムズムズ

生後3〜6か月頃、乳歯が抜けて永久歯に生え変わります。
乳歯の頃と永久歯では噛む力が全く違い、永久歯になると甘噛みでも痛さが段違いです。
生え変わりの違和感から噛みたくなるのは自然ですが、ここでの対応次第で習慣化や要求噛みにつながります。
愛情表現や安心のサイン

猫ちゃんは信頼している相手にだけ「なめる・噛む」という行動を見せることがあります。
甘噛みは「大好きだよ!」というサイン。
愛情表現だと理解しつつも、エスカレートしない工夫をすることが大切です。
初心者飼い主が戸惑った、甘噛みエピソード

うちのサビ猫♀は生後5週齢で我が家に来ました。
6ヶ月齢前後から、私が座っていると髪を引っ張ったり、立っていると内ももを噛むように。
完全に要求咬みで、痛くて応えるしかない状況でした。
家に来た頃から、指を目で追う姿が可愛く、つい手で遊んでしまうこともあり、それが噛み癖を助長していたことに後で気がつきました。
子猫の甘噛みをやめさせる方法
噛まれたら遊びをやめて無視する

わんちゃんのしつけでもよく言われる、噛まれたときに声をあげたり、遊び続けると「噛めばかまってもらえる」と学んでしまう悪循環。
一度学習してしまうとエスカレートするため、噛んだらその場を立ち去るか、遊びを終了しましょう。
ただし痛すぎて応えざるを得ない場合は、他の方法で注意をそらすことが大切です。
噛んでいいおもちゃを与える

素手で遊ぶのではなく、お気に入りのおもちゃで攻撃対象を切り替えます。
但し、お気に入りの噛みごこちのおもちゃでないとすぐにまた噛んでくるので、大きさや固さ、素材などさまざまなものを試して、お気に入りのものを探しましょう。
猫ちゃんは蹴り蹴りするのも好きなので、ガブガブ&蹴り蹴りできる大きさのものがおすすめです。
わが家では100円ショップのくまさんパペットやウサギの猫じゃらしが大ヒット。
これで手への攻撃はほぼ解消しました。
たっぷり遊んで発散させる

“噛む=無視する=遊ばない”では猫ちゃんのストレスが溜まってしまいます。
十分に遊んでエネルギーを発散させてあげることも大切です。
猫ちゃんが噛んでくるタイミングをよく観察してみると、噛むことが猫ちゃんなりの「遊びの誘い」のことがよくあります。
「最近やけに噛んでくるなぁ」
と思ったら、一緒に遊んであげる時間を確保できているか、振り返ってみましょう。
遊びに満足するとすやすや気持ちよさそうにぐっすり寝てくれるかもしれませんよ。
ついやってしまいがちなNG対応
叩いたり怒鳴ったりする

体罰や、大きな声で叱ることは恐怖心や不信感を生むだけで、逆効果です。
猫ちゃんは自分が悪いことをしたとは理解できないため、絶対にやめましょう。
手をおもちゃ代わりにする

手で遊ぶと「手=噛んでいいもの」と学習してしまいます。
毎日の小さな積み重ねが習慣化の原因です。
噛まれたときに反応するのは逆効果

「痛い!」「きゃー!」「コラッ!」「ダメ!」とつい反応してしまいますが、その反応を猫ちゃんは「遊び」と認識し、甘噛みをエスカレートさせてしまっているかもしれません。
噛まれたときは、「冷静に、静かに立ち去る」のが最も効果的です。
元動物看護師目線でのアドバイス
放置すると「本気噛み」に発展するリスク

甘噛みを放置すると、成猫になっても噛み癖が残り、人や他の猫ちゃんに危険を及ぼすことがあります。
猫ちゃんの咬み傷は小さく見えても、化膿しやすく、点滴治療になることもあるため、注意が必要です。
出血するほどの咬傷を負った場合は、必ず当日中に整形外科か皮膚科を受診しましょう。
病院勤務で、筋肉にまで到達するケガをしたことが2度ほどありますが、のちに飼い主さんから話を聞くと日常的に手を噛んでいたことがわかりました。
飼い主さん:
「普段は甘噛みなんだけどね〜。時々本気で咬んで私も何度か病院に行ったのよ〜!」

え…。
人を噛むことに慣れてしまった猫ちゃんは飼い主さんや他人にケガをさせてしまう可能性が高まり、とても危険です。
甘噛みだからと放置せず、人を噛ませないように工夫しましょう。
どうしても改善しないときは病院に相談も

猫ちゃんが急に本気で噛むようになった場合、病気が潜んでいる場合があります。
- どこかが痛い
- 強い不安感・恐怖心がある
- 脳の病気
以前、病院を受診した猫ちゃんのお話です。
飼い主さんと一緒に寝ていたWちゃん♀。夜中に突然飼い主さんの足を思い切り咬んでしまい、大怪我をした、ということでした。
診察の結果、皮膚と脳の病気が判明し、飼い主さんが触れた刺激で“猛烈な痒み”に襲われたWちゃんが、発作的に噛んでしまう、ということがわかりました。
このケースはまれなパターンですが、病気が隠れている場合は治療によって改善することもあるため、動物病院に相談しましょう。
そして、行動に問題がある場合は行動学に詳しい獣医師やトレーナーを紹介してもらうのも、とても有効です。
かかりつけの動物病院に相談してみましょう。
まとめ:子猫の甘噛みと上手に向き合うために

子猫の甘噛みは成長過程でよくある行動。
「遊びたい」「歯がムズムズする」「大好き!」という気持ちの表れでもあります。
ただし放置すると噛み癖に発展し、成猫になってから困ることに。
私も最初は可愛いからと許してしまい、手が傷だらけになりましたが、対応法を工夫することで改善できました。
ポイントは、
- 噛まれたら遊びをやめる
- おもちゃで気をそらす
- 冷静に対応する
この3つを意識するだけでも変化が見られます。
焦らず、信頼関係を大切にしながら、猫ちゃんとの生活を楽しみましょう!
▼合わせて読みたい
▼参考リンク(外部サイト)
動物行動学専門のクリニックです。とても勉強になります。ぎふ動物行動クリニック
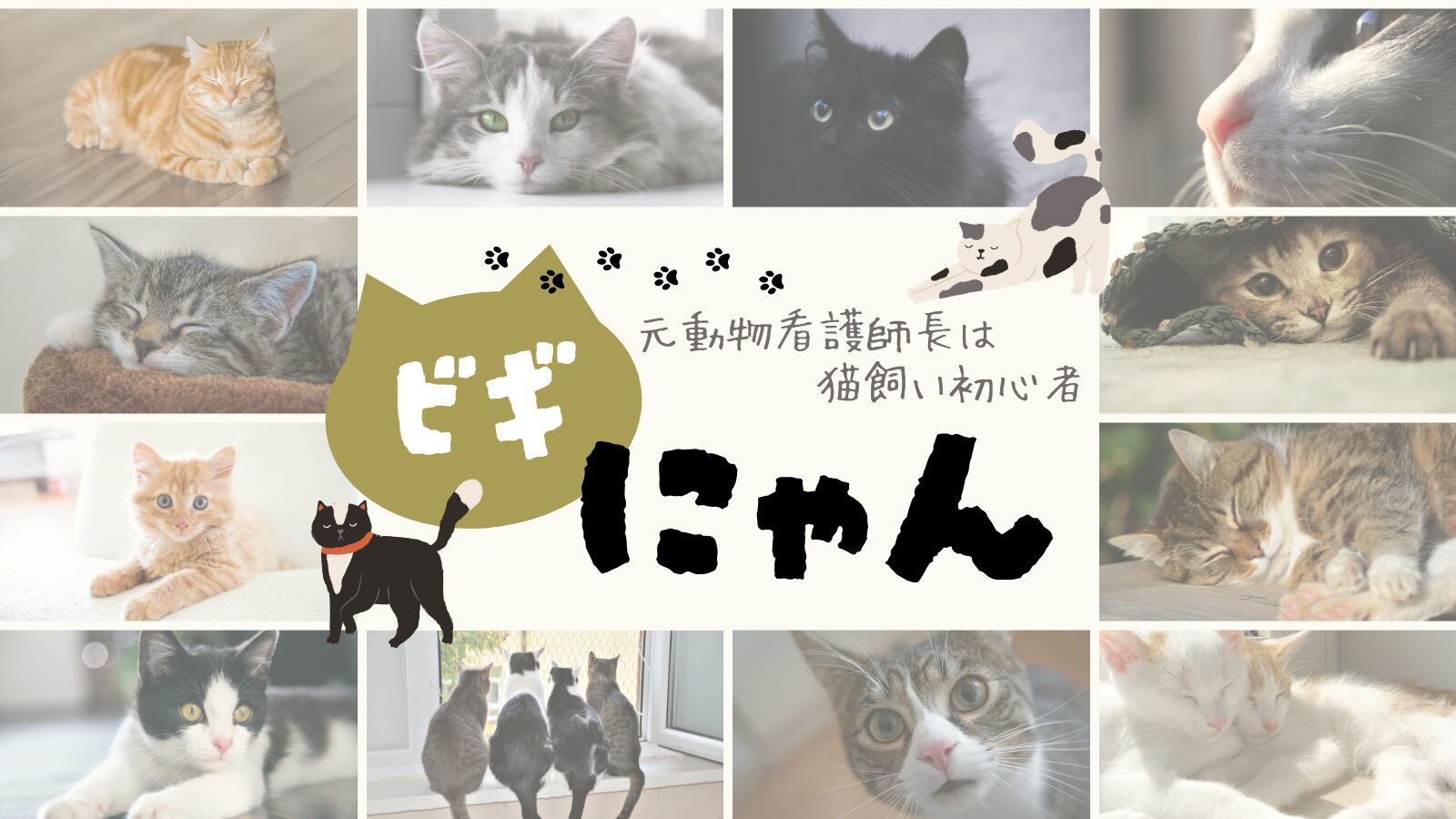


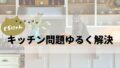
コメント