「動物病院で使われる用語の意味がわからず、説明が頭に入ってこない」
「なんとなくはわかるけどぼんやりとしていて、似ている用語との違いがわからず混乱する」
そんな経験はありませんか?
用語の意味を改めて知ることで獣医さんや看護師さんからの説明がすんなり入ってきて、安心して聞けるようになりますよ。
本記事では元動物看護師の経験から、初心者飼い主さんがわかりやすいように用語を解説します。
動物病院でよく聞く用語
診察中よく耳にする用語

診察中、よく目にする聴診や触診。実際何を診ているのかよくわからなくて、軽視してしまいがち。
しかし聴診や触診でわかることはたくさんあるため、実はとても大切です。
検査に関する用語
症状に応じて必要な検査を獣医師が選択し、治療方針を決めていきます。
- それぞれ、なんとなくイメージはできてもいまいち何をどう診ているのかわからない
- イメージが似ているものは混同してしまう
- 画像を見て説明を受けてもそもそも見方がわからない
- 麻酔は必要?不要?
親切な獣医師であればわかりやすく説明してくれるので理解しやすいのですが、全員がそうとは限らないので基礎知識として覚えておくと役立つことをまとめました。
血液検査

◯猫ちゃんの場合、採血は後肢の内側、首、前脚の血管から採ります。
◯わんちゃんは、前脚、後肢の外側、首から採ります。
- 目的に合わせて検査する項目を獣医師が選択
- 検査項目に必要な量の血液を採る
- 院内検査か外部の検査機関へ依頼
- 数値を見て体の状態を評価する
◎院内検査 所要時間:30分〜1時間程度
◎外部機関へ検査を依頼する場合は、項目によりますが1週間程度で結果が出るでしょう。
後日、結果を電話で説明してくれるか、再度来院指示があるか、病院の方針により異なります。確認しておきましょう。
レントゲン検査
X線で体の中を写す検査。
“写真”と表現する獣医さんも。
被爆を防ぐため、飼い主さんはレントゲン室には入れません。鉛の入った防護衣を着たスタッフが撮影します。
一般的によく行われる検査の一つで、主に骨折や内臓の腫れ、尿石や異物誤食の際に用いられます。
【レントゲン画像の見方基本ルール】

- 骨、石などの固いもの→白
- 気体・液体→黒
- 横向き画像は頭が左
- 縦向き画像は頭が上
レントゲンは固いものほど白くはっきりと写るため、異物誤食の際、金属や石などはとてもくっきりと写りますが、布や毛玉などの場合は写りにくく、バリウムを用いることもあります。
エコー検査

超音波で体の中をリアルタイムで確認でき、さまざまな診断に用いられます。
体内で液体が溜まっているところは基本的には心臓と膀胱だけなので、その他に液体が溜まっているところがないか、その大きさや深度はどれくらいか、詳細に観察できます。
体内のしこりに針を刺して成分を調べる検査の際にも役立ちます。
そして心臓の弁や血流まで確認できるため、心臓の診察にもよく用いられます。
膀胱結石・結晶のときにはまるでスノードームのように見えます。
CT検査
レントゲンと同様、X線で体の中を写す検査。
少しずつずらしながら大量のレントゲン写真を撮って、全体像を掴むイメージです。
椎間板ヘルニアのとき、レントゲンでは映らない椎間板部分を確認できます。
導入している病院は多くはありませんが、大きな手術をする際、詳細を確認できるのでとても役立ちます。
検査費用は2〜5万円程。
※検査自体は数秒〜数分で終わりますが、静止が必要なため、動物は要麻酔です。
MRI検査
強力な磁石と電波であらゆる方向から撮影し、立体的に画像化する検査です。
費用は15〜30万円程でかなり高額ですが、脳や血管の走行まで確認できます。
筆者の勤めていた病院では脳外科などの大きい手術のときに用いられていました。
一般の動物病院ではあまり導入していないので、必要になったときにかかりつけ医から大きな病院を紹介してもらい、行うような検査です。
検査所要時間は1時間以上要することもあり、要麻酔。
直腸検査(直検)(ちょっけん)
肛門に指を入れて直腸に異物やしこり、圧迫がないかなどを調べる検査。
手袋と局所麻酔のゼリーを用いて無麻酔で行うことが多く、摘便と同じ要領なので診察の際にその場でぱっと終わることが多いです。
内視鏡検査
麻酔をかけて、カメラが付いた管を口または肛門から挿入し、消化器官の中を観察します。
必要に応じて異物や組織を採取することも。
尿検査
便検査
処置でよく使われる用語

【ネブライザー】
鼻水や痰で呼吸がしづらいときなどによく行われます。
密閉したケージの中に薬剤を霧状にしたものを充満させてしばらくその中で過ごしてもらう処置で所要時間は30分程です。
数繰り返して行うことが多い処置です。
【摘便(てきべん)】
肛門に指を入れて便を掻き出す処置で、便秘や、事故の後遺症等でうまく排便ができない場合などによく行われる処置です。
便の溜まり具合によっては毎日する場合も。
無麻酔ですることが多いため、猫ちゃんが大嫌いな処置です。
【催吐処置(さいとしょち)】
異物誤食のときに薬剤を使って、嘔吐を促します。※無麻酔
誤食の内容によっては吐かせない方がいいものもあるため、獣医師の判断で内視鏡での処置に移行することもあります。
【挿管(そうかん)】
麻酔をかけたときや、エマージェンシー(救急救命)のときに気管チューブを気管内に挿入し、酸素循環を助けます。
お薬や注射でよく使われる用語

動物病院では、「薬」や「注射」の説明を受ける機会が多いですよね。
でも聞き慣れないものばかりで頭に入ってこない…そんな経験はありませんか?
ここでは、飼い主さんが説明中によく耳にする用語を中心に、意味や注意点をやさしく解説します。
意味がわかるだけで、不安が減ったり、納得感が増したりするのでぜひ覚えておきましょう。
よくある薬の種類とその意味

抗生剤(こうせいざい)
- 細菌感染を抑える薬
- 種類が豊富
- 飲み薬・注射・外用薬など形状はさまざま
- 下痢や嘔吐をしてしまうことも
※自己判断で中止せず、獣医師の指示に従いましょう。副作用等が表れた場合は必ずかかりつけ医に相談しましょう。
消炎剤(しょうえんざい)
- 炎症を抑える薬の総称
- 痛み止めも含まれる
- NSAIDs(非ステロイド系)やステロイド系に分けられる
※必ず獣医師の指示を守って投薬しましょう。
ステロイド
- 強い消炎作用がある
- アレルギーや自己免疫疾患の治療でよく使われる
※使用方法は必ず獣医師の指示に従いましょう。
駆虫薬(くちゅうやく)
- お腹の虫(寄生虫)やノミ・ダニを駆除する薬
- 動物病院ではよく使われる
- 種類が豊富
- 滴下薬、内服薬、注射など形状がさまざまで、生活スタイルに合わせて選択できる
- 月に一回の投与が一般的
- 3カ月に一度の投与で済むものもある
注射・点滴でよく出てくる用語

【筋肉注射/皮下注射/静脈注射】
- 注射方法の名称
- 薬剤の種類によって注射する方法が決められている
- 皮下注射が一番痛みが少ない
【皮下点滴(ひかてんてき)・皮下補液(ひかほえき)】
- 皮膚の下に水分や薬を入れてゆっくり吸収させる治療法
- 脱水や腎臓病など多くの場面で使われる
- 痛みが少ないため家庭ですることも多い
【インターフェロン】
- 免疫を高める注射
- 猫ちゃんの風邪の治療によく用いられる
- 点眼薬や点鼻薬に混ぜて使用することも
- 他の注射と比べると高額
- 点滴を流す針を血管に入れたままにすること
- 通院点滴の場合は抜かずにそのまま針を入れたまま帰宅することも(※毎日入れ直すと血管が潰れて点滴ができなくなってしまうため)
- 急変したときにもすぐに対応できる
【点滴/静脈点滴】
血管に留置した針にチューブを繋いで点滴液を流します。
動物は身を縮めてしまうため、前肢に入れることが多いです。
飼い主さんに知っておいてほしいこと

わからない言葉が出てきたら、遠慮なく質問しましょう。
話を録音したり、メモするのも◎。緊張で内容を忘れてしまうのはよくあることです。
※録音する場合は一言添えると良いでしょう。
処方されたときにチェックしたいポイント

◎用法・用量:必ず決められた回数・量を守りましょう。
⚠自己判断でやめるのはNG。
◎保存方法:冷蔵保存が必要な薬もあります。受け取るときに確認を。
◎形状:錠剤、粉、液状、チュアブルタイプ(おやつ風)などさまざま
◎副作用の有無:嘔吐・下痢・元気がなくなるなど、異変が出たらすぐに病院へ連絡しましょう。
意外と知らない点◯薬

- 点眼薬(てんがんやく)
- 点鼻薬(てんびやく)
- 点耳薬(てんじやく)
字で見ると意味がわかりやすいけれど耳で聞いたり、口に出したりすると意外と戸惑うこの3種類。
病院で勤務していて、これらを混同している飼い主さんがとても多かったです。
字を見て確認しておくとなんだかすんなり入ってきます😊
知っておきたい診療明細のポイント
◎料金の基準は動物病院ごとに異なります。
自由診療なので、同じ処置でも金額に差がある場合があります。
◎初診料は初めて病院を受診した日だけにかかるものではありません。
※「初めてその病気・症状で受診した場合」=初診料として計算されます。
まとめ

飼い主さんが動物病院での用語の基本を知っておくと、説明を聞くときにも理解がスムーズで、治療内容を正しく理解しやすくなり、安心感が増すことに繋がります。
動物医療の世界には、人間と同じようにたくさんの専門用語があります。
すべてを覚える必要はありませんが、「よく耳にする言葉」や「処方内容」などを少しずつ理解することで、より安心して通院・治療を進めることができるようになります。
そしてわからないことは遠慮せずに聞いてみましょう。丁寧に教えてくれるはずですよ。
▼あわせて読みたい
▼参考リンク(外部サイト)
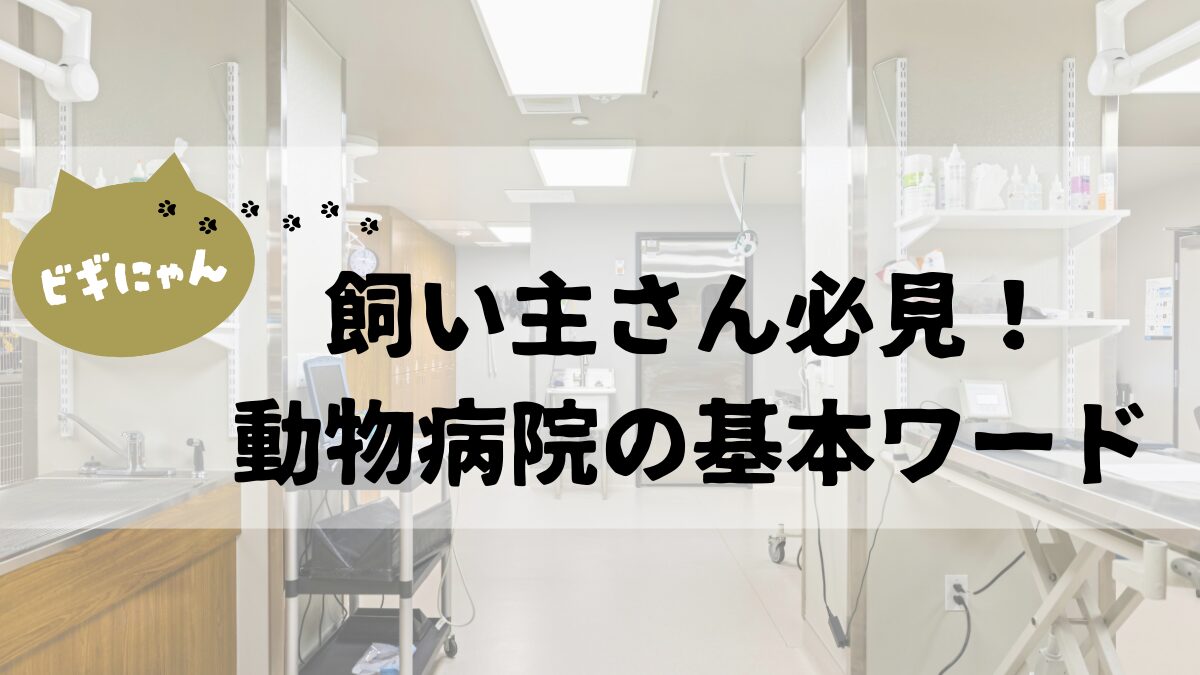
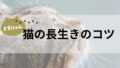
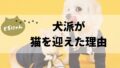
コメント