
子どもに動物と暮らす経験をさせてあげたいけど…。
- お世話は結局親がすることになるんでしょ?
- ケガしたり、させたりしないかな?
- 仲良くできるのかな?
- 旅行やおでかけができなくなる…?
- 家事・育児・仕事でただでさえ忙しいのに猫が増えたら…大丈夫かな?!
考えれば考えるほどなかなか踏み出せない…筆者宅では家族でたくさん話し合いを重ねました。
猫ちゃんを迎えるに至った経緯と、迎えてから実際に子どもに与えた影響と子どもとの関係性を具体的にお伝えします。
猫ちゃんと子どもが一緒に暮らす上での魅力と注意点をイメージしやすくなっていますので、ご家族でたくさん話し合って、デメリットも理解した上で、猫ちゃんを迎えるきっかけになれたら嬉しいです。
筆者宅が猫を迎えるに至った経緯

筆者は40代の夫と小学生の息子との3人暮らしです。
夫婦ともに幼少期からさまざまなペットと暮らした経験があり、息子にも同じ経験をさせてあげたいという気持ちを持ちつつ、数年が経過しました。
犬がいいか、猫がいいか、ウサギがいいか、モルモットがいいか…そんな話を何度も繰り返す日々。
ふと、

息子への情操教育の時期、逃すんじゃなかろうか?!
“いつか”迎えるなら早い方がいいのでは…!?
私が仕事を退職したこともあり、本格的に話し合うことにしました。
話し合う中で、“犬か、猫か”の2択に。
- 私は犬派で猫飼い経験なし
- 夫は両方経験ありの猫派
- 息子は犬好きの猫派
▷猫に2票、犬に1票
- 仕事と家事と子育てで毎日犬の散歩はできるのか→自信なし
- 月に一回トリミングへ連れていけるか(時間面・費用面で続けられるか)→自信なし
- 一番面倒をみるであろう筆者が犬派
▷猫にさらに2票、犬に1票
また答えが出なそうな気配…すると、
主人:「猫きらい?」
私:「好き❤」
主人:「じゃぁ、いいじゃん」
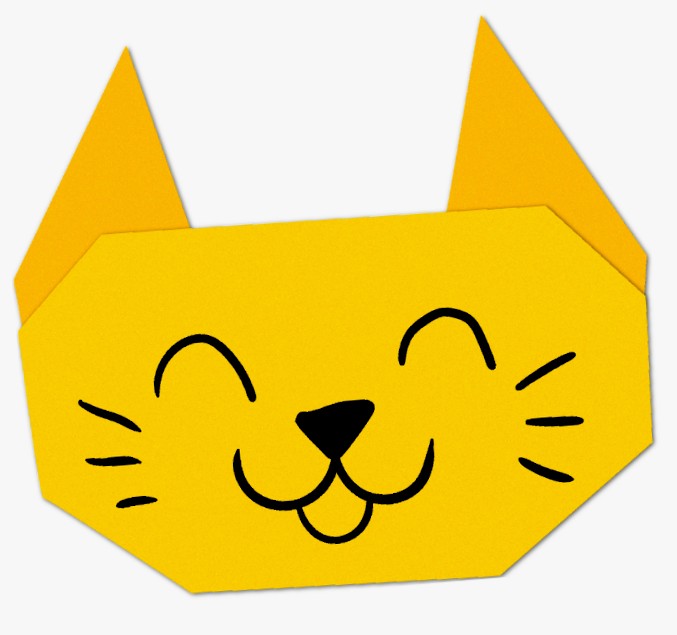
犬派でも、猫が好きならそれでいいんだ!!(目から鱗)
猫ちゃんに決定した瞬間でした。
そこから里親募集サイトを通じて生後5週齢のサビ猫ちゃん♀を迎えることになりました。
子どもと猫の関係性

家に来たときはまだまだよちよちの小さい子猫。
家族全員で「ケガをさせないように」と慎重に過ごし、いつもドタバタ騒がしい息子を何度も叱る日々(笑)
徐々に猫ちゃんがいる生活に慣れてきた息子は少しずつ慎重に行動するようになりました。
初めての猫ちゃんとの生活に喜びを感じている様子。
やさしく撫でたり、抱っこをしたり、構いすぎないようにそっと観察したり。
息子は少し赤ちゃん返りするも、猫ちゃんには優しく接しています。
そして少し大きくなってきた猫ちゃんは息子を狩る毎日(笑)
なぜか息子にだけいつも襲いかかっています。
髪を引っ張ったり、陰に隠れて突然飛び出して驚かせたり…そんな1人と一匹はまるで兄妹のよう。
家族全員が猫ちゃんに癒されています。
そして共通の、“守るべき存在”“癒しの存在”ができたことで家族に柔らかい空気が流れるようになった気がします。
猫が子どもに与える影響

実際に猫ちゃんを迎えてみて、子どもの成長を感じる出来事がありました。
1年ほど登校しぶりのため、母子登校をしていた息子が、猫ちゃんを迎えて3か月、母なしで学校で過ごせるようになりました!
猫ちゃんの存在だけが理由ではありませんが、猫ちゃんとの触れ合いやお世話を通して家庭での自分の役割ができ、“守られる存在”から“守る存在ができた”ことが自信に繋がったように見えます。
子どもの情緒を育てる効果

子どもにとって、言葉を使わずに心を通わせられる存在はとても大きな意味があります。
心理学的にも、ペットとの触れ合いはストレスを軽減し、情緒の安定を助けると報告されています。
私自身、子どもの頃、犬やうさぎ、鳥などさまざまなペットと暮らしてきました。
親とけんかしたときや、友だちとトラブルがあったときなど動物たちはそっと寄り添い、癒してくれました。
そんな経験から得られるものはとても大きかったと感じています。
子猫と息子との関わりを見ていて実感するのは、“動物にしか担えない大きな役割がある”ということです。
猫ちゃんを迎えて本当によかったです。
思いやりや命の大切さを学べる

猫ちゃんと一緒に暮らすことで、子どもは「自分以外の存在を大切にする」という貴重な経験を積むことができます。
ごはんをあげたり、トイレを掃除したり、毎日のお世話を通じて“大切にするべき存在”と認識を深めていきます。
また、猫ちゃんは時には体調を崩すこともあります。
病院に連れて行く経験や、心配したり、看病したり、そして年をとっていく様子を見守る過程は、子どもに「命の大切さ」「弱い存在への思いやり」を自然に教えてくれます。
これは学校の授業では得られない、かけがえのない学びです。
子どものストレス軽減と安心感
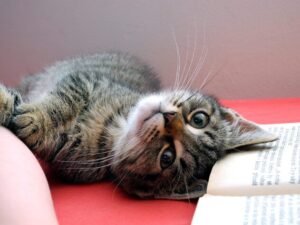
猫ちゃんと触れ合うことで、安らぎと癒しを得ることができます。
猫ちゃんのやわらかな毛並みを撫でると、落ち着き、リラックス効果が得られるという研究結果もあります。
子どもが日常生活で抱えるストレスは、大人が思っている以上に大きいもの。
学校での人間関係や勉強へのプレッシャーなどを抱えていても、猫ちゃんと一緒に過ごすことが気持ちを切り替えるきっかけになることもあります。
また、猫ちゃんは言葉を使わない分、子どもは「自分の気持ちをそのまま受け止めてくれる存在」と感じやすいのです。
抱っこをしたり、猫ちゃんが横に寄り添ったりするだけで、子どもは安心感を得られるのです。
大人はつい言葉に頼りがちですが、動物は存在そのもので励ましてくれたり、寄り添ってくれます。
そしてこどもだけでなく、家庭全体に与える影響の大きさも日々実感しています。
癒しを与えてくれるため、イライラすることが減り、笑顔が増えました。
そして猫ちゃんのおもしろエピソードなど、家族の共通の話題が増えました。
猫ちゃんを通して家族全員が笑顔になれる——これこそが「猫ちゃんと子どもが一緒に暮らす最大の魅力」です。
自立心や責任感が育つ

猫ちゃんのお世話は毎日欠かせません。
ごはんをあげる、水を替える、トイレを掃除する——毎日継続して行う必要があります。
少しずつ子どもに役割を分担していくことで、「愛着」と「責任感」を育てるきっかけになります。
年齢に応じて少しずつ任せていき、「自分がやらないと猫ちゃんが困る・かわいそう」という実感をもつことが、子どもにとって大きな学びになります。
親に「やりなさい」と言われて仕方なくやるのではなく、猫ちゃんのために自主的に動けるようになることは、思いやりや責任感の芽生えにつながります。
その芽を摘まずに、褒めて育てて、習慣化を目指しましょう。
猫ちゃんに危険がない範囲で、手を出さずに見守ること・任せることも大切です。

家事・育児・仕事で忙しい大人に、さらに猫ちゃんのお世話が丸々追加されるのはなんとしても避けたい!!(心の声)
多少のことには目をつむり、子どもの役割を少しずつ増やしていきましょう。
学習や集中力へのプラス効果

「ペットがいる家庭の子どもは集中力が高まりやすい」という研究結果があります。
猫ちゃんと暮らすことで学習や集中力に良い影響が出るなんてありがたすぎる!!
また猫ちゃんに話しかけたり、一緒に遊んだりすることはコミュニケーション能力の発達にもつながります。
「どうすれば猫ちゃんが喜ぶかな?」と考えること自体が、相手を思いやる力や想像力を鍛えます。
こうした日常のやりとりが、結果的に学習意欲や社会性の成長を後押ししてくれるのですね。
猫と子どもが安心して過ごせる環境づくり
猫専用の逃げ場所をつくる

猫ちゃんは静かな環境で、自分のペースで過ごすことを好みます。
でも子どもが元気に動き回るのをあまり制限しすぎたくないのも親心。
猫ちゃんのために落ち着ける場所を確保してあげるのが重要です。
例えば…
- キャットタワーの高い位置
- 子どもが入れない部屋を確保する
- ケージやちぐらの中
など、「ここにいれば安心」というスペースを確保してあげましょう。
「そこにいるときは放っておいてあげてね」など、子どもと約束事を決めておくことで、猫ちゃん自身のストレスを防ぎ、子どものケガを防ぐことにも繋がります。
猫ちゃんの特性を把握しておく
猫ちゃんのいやがること
猫ちゃんはストレスに弱い動物です。
嫌なことをすると咬んだり、ひっかくだけでなく、ストレスにより膀胱炎などの病気になってしまうこともあります。
猫ちゃんのいやがることを家族で確認しておきましょう。
- 無理矢理抱っこをする
- 寝ているところを起こす
- 食事中・排泄時に触る
- 大きな音をたてる
- しつこく構う
- しっぽや手を掴む 等
猫ちゃんとの生活で気をつけること
猫ちゃんは好奇心旺盛で俊敏な動物です。
猫ちゃんは、少しの隙間に入ろうとしたり、ドアが開いた瞬間にすり抜けたりするため、思わぬ事故に繋がることもあるため、注意が必要です。
- 窓やドアを開けっ放しにしない
- 少しの隙間に入ろうとするため、閉じ込めや、挟み込みなど注意が必要
- 好奇心旺盛なのでゴミやお風呂も注意
わが家の猫ちゃんは食洗機の中に入ろうとするので、急いで閉めて猫ちゃんの指を挟んでしまった…ということがあります。
息子がリビングのドアを閉める際、出ようとした猫ちゃんの指を挟んでしまったこともあります。
⚠猫ちゃんの行動をよく把握し、子どもも猫ちゃんもケガをしない、させない工夫が必要です。
清潔と安全への配慮

子どもと猫ちゃん、両方の安全のためにできることがあります。
- トイレや水飲み場は、子どもが遊ぶスペースから少し離す
- 誤食を防ぐため、おもちゃや小物は散らかさない
- 定期的にブラッシングや爪切りをする
- 病院で寄生虫の感染の有無を確認&予防をする
- 猫ちゃんの嫌がることをしない、など子どもと約束事を決めておく
◎衛生面の配慮は、子どもと猫の両方の健康につながります。
まとめ

子どもと猫ちゃんが一緒に暮らすときは、最初のルールづくりや接し方の工夫がとても大切です。
◎猫ちゃんが安心できる環境を整える
◎子どもとルールを決める。「寝ているときは触らない」など
◎お世話に関わりをもたせる
この3つを意識するだけで、猫ちゃんも子どもも安心して仲良く過ごすことができるでしょう。
家族全員で工夫しながら、猫ちゃんと子どもの素敵な関係を築いていきましょう。
▼あわせて読みたい
▼参考リンク(外部サイト)
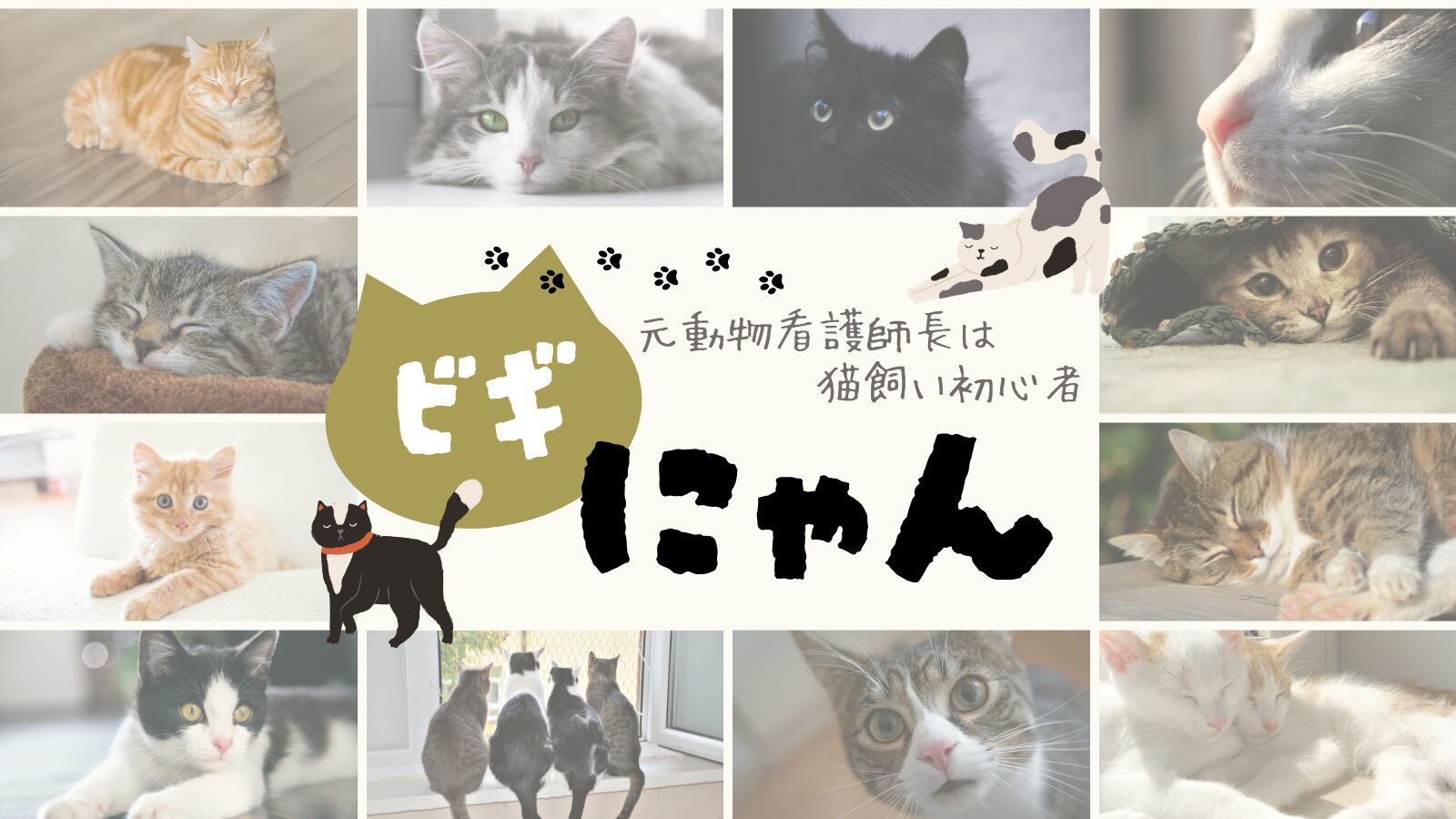

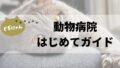

コメント