初めて動物病院へ行くのは、ドキドキしますよね。
- 何を持っていけばいいの?
- どんなことを聞かれるの?
- うまく答えられるかな?
- どんな雰囲気なんだろう。
- いくら持っていけばいいの?
- 獣医さんが怖かったらどうしよう。
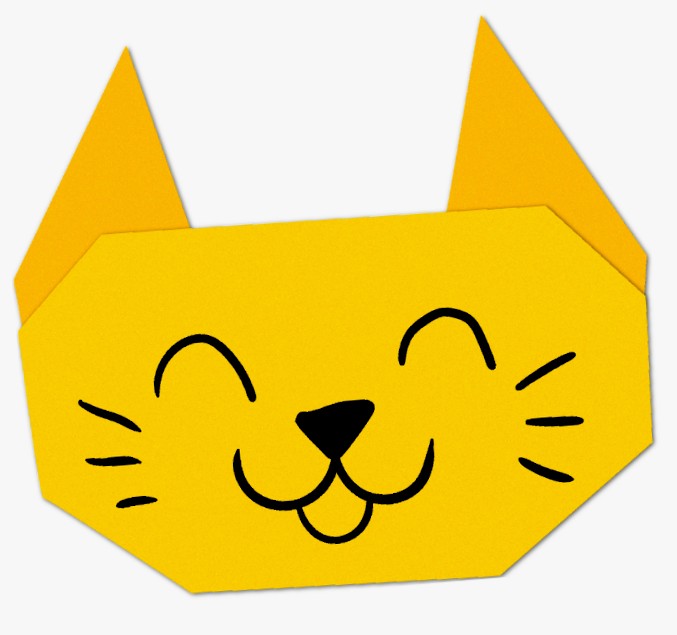
準備や流れを知っておけば安心して受診できますよ。
本記事では、元動物看護師の視点から、
- 初診当日の流れ
- 持ち物
- よく聞かれる質問
- 費用の目安
- 受診前後の注意点まで
をまとめてわかりやすく解説します。
初めて猫を動物病院へ連れて行く前の準備
キャリーケースは必須アイテム

まず、病院へ連れて行くための準備としてキャリーケースは必須アイテムです。
環境の変化が苦手な猫にとって、外出そのものが大きなストレスになります。
少しでも安心して過ごせるよう、必ずキャリーケースを用意しましょう。
特に、キャリーに慣れていない猫ほど、当日いきなり入れようとすると、不安になりやすく、診察が延期になるケースもあります。
受診日から逆算し、キャリーに慣れる時間もあらかじめ考慮しておくことが大切です。
▼あわせて読みたい
病院選びは重要

どこの病院に行くかは「病気になってから考える」のではなく、事前にいくつか候補を挙げておきましょう。
ワクチンや爪切りなどの目的で、何軒か受診してみてから、かかりつけ医を決めるのがおすすめです。
▼あわせて読みたい
予約制の有無を確認

予約が必要かどうか確認しておきましょう。
電話予約・ネット予約・紹介のみの病院もあります。
事前によく確認しておくと診察までがスムーズです。
持ち物
猫ちゃんの情報がわかるもの

初めて受診するときは猫ちゃんの情報がわかるものを持参しましょう。
- ワクチン接種証明書
- ペット保険証券(加入していれば)
- マイクロチップ登録証
- ペットショップやブリーダーからもらう“既往歴やワクチン接種履歴”が書かれたもの(あれば)
- 病状を記録したもの(下痢、食欲等を記録しておくと役立ちます)
普段の様子がわかる人が連れて行くことも重要です。
⚠状況を把握していない人が連れて行く場合は詳細を書いたメモを持参するなど、配慮が必要です。
安心・安全を守るアイテム

猫ちゃんの安心・安全のために以下のものを用意しましょう。
- キャリーケース
- いつも使っているタオルや毛布等(キャリーに敷いてあげましょう)
- ペットシーツ(万が一の排泄の備え)
- おやつ(診察時または診察後に与える)
- 暴れる場合は洗濯ネットに入れてからキャリーケースに入れると診察がスムーズでおすすめです◎
【元動物看護師推奨】初診時に便を持参

元動物看護師として持参をお勧めするのが、“便”です。
下痢等の症状がなくても寄生虫がいる可能性は十分考えられます。
お家に迎えたら、初めて病院に行く際に、当日の便を持参し、検査してもらうことで安心して生活を送ることができます。
親指の先ほどの量があれば検査可能なので、ラップ+袋や、ジップ袋に入れて持参しましょう。
その他の持ち物

なにか気になる症状がある場合はその材料を持参すると診断がスムーズです。
▶血尿・頻尿→尿を液体のまま(⚠ペットシーツやおむつに吸ったものは検査不可❌️)
▶嘔吐→嘔吐物の写真を撮っておく
▶誤食→現物(成分表)
▶咳や発作、行動の異変→動画があるととても役立ちます。
診察の際、たびたび経験したのは、飼い主さんが言う“けいれん”と、病院側の“けいれん”の認識のずれが非常に大きいことです。
実際に動画を見せてもらうと、震えや、しゃっくりのことが多く、その場合、治療の方向性が大きく異なるため、動画の情報は診断にとても役立ちます。
支払い方法を確認しておく
見落としがちなのが支払い方法です。
現金だけ、現金とPayPayだけ、一部のクレジットカードが使用不可等ありますのでホームページや電話で確認しておきましょう。
▷加入しているペット保険に対応しているかどうかも確認しましょう。
対応している保険会社が病院により異なるため、確認しておくと安心ですね。
費用の目安
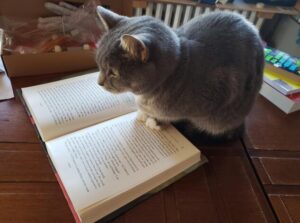
保険に加入していない場合、全額窓口で支払うため、人の精算額と比べ、高額に感じるかもしれません。
大体のめやすを知っておくことで準備ができますね。
診察料

▷初診料→1500〜3000円
これは“初めて行った時だけ”ではないので、注意が必要です。
“その病気で初めての受診”のとき全てにかかります。
例えば…
- 下痢で受診《初診料》→完治
- 数カ月後、同じ症状で受診《初診料》
同じ病状であっても一度改善し、期間が経つと計算上は“別の疾患”ということになります。
病院によってその条件はさまざまですが初診料が“初めて受診した時のみ”ではないことだけは頭に入れておきましょう。
実際、「初診じゃないのに初診料になってる」という問い合わせを受けたことが何度もあります。
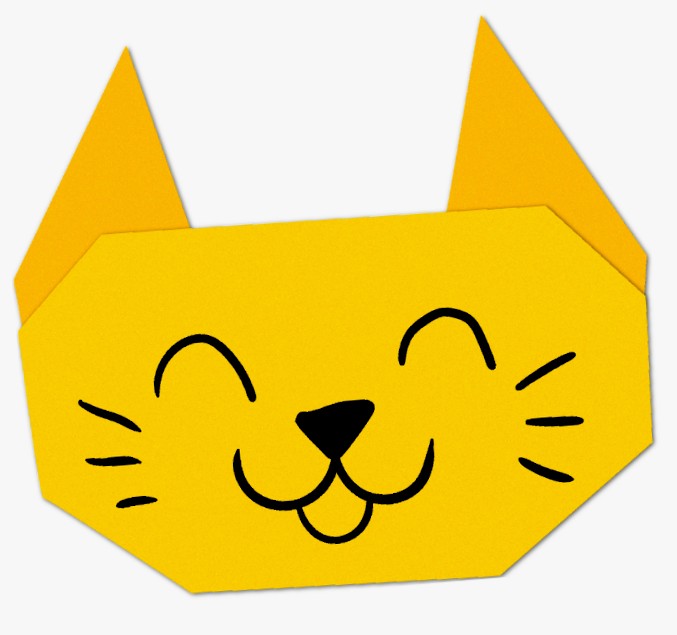
“初診料”は“その病気を初めて診るときに”かかるということを覚えておきましょう。
通常、診察料(初診料・再診料)に検査代や薬代などが加算されていきます。
ワクチンや検査にかかる費用

初めて受診したときに、健康状態に応じてワクチン接種や検査が追加されることがあります。
▷よくある項目と目安費用
- 混合ワクチン:4,000〜6,000円/回
- 猫エイズ・白血病ウィルス検査:4,000〜6,000円
- 便検査(寄生虫の有無):1,000〜2,000円
- 血液検査:5,000〜10,000円
- ノミ・ダニ予防薬:1,500〜2,500円/月
- フィラリア予防薬:1,500〜3,000円/月
猫の年齢・生活環境・体調に合わせて獣医師と相談して決めていきます。
そして獣医師の指示する回数・タイミングは必ず守りましょう。
※費用・予防期間は地域・病院・猫の状態によって大きく異なります。
実際の診察の流れ

初めての動物病院では、飼い主さんも猫も緊張してしまいます。
大まかな流れを知っておくと安心です。
受付・問診票の記入
受付をする

受付で「今日はどうされましたか?」と聞かれたら簡潔に答えましょう。
詳細は問診票もしくは診察室で詳しく答えるのが一般的です。
- おとといから下痢をしている
- 今朝から歩き方がおかしい
- 3日前から食欲が落ちていて、今朝から何も食べない 等
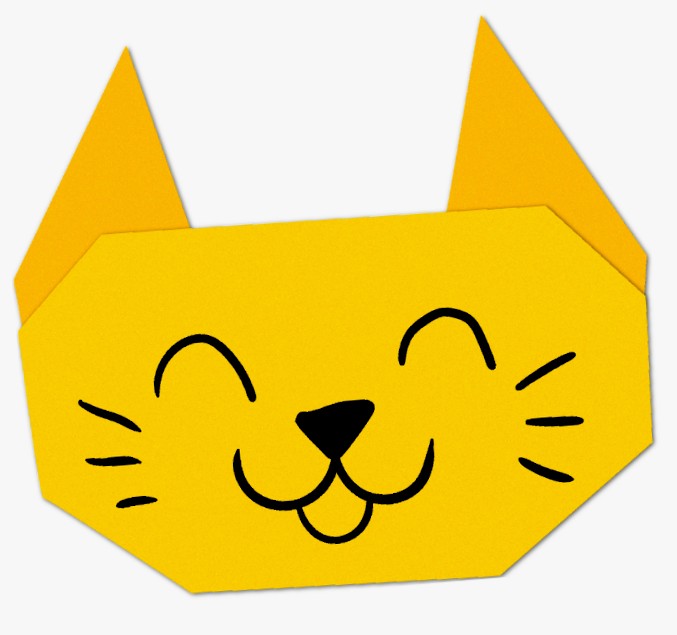
「いつからどのような状態の為、病院に来たか」を簡潔に伝えましょう。
問診票の記入

- 飼い主の住所・氏名・連絡先
- 猫の名前
- 生年月日
- 品種
- 性別(不妊手術済or未)
- 既往歴
- ワクチン接種歴
- 病状の経過 などを記入
これらの情報は記入できるように準備しておきましょう。
受付・問診票の記入が終わったら受付に提出し、待合室で順番を待ちます。
待合室で待機

犬や他の猫の鳴き声や視線でストレスを受けやすいので、キャリーに布をかけてあげましょう。
犬と猫の待合室が分けてある病院もあります。
順番が来るまで車で待機することができる場合もあるので受付で確認してみましょう。
診察の大まかな流れ

①診察室に入ったら、指示があるまでは猫をキャリーから出さずに待機しましょう。
②獣医師から猫の普段の生活や症状について質問されます。
③食欲・排泄・行動の変化を具体的に答えられるようにしておきましょう。
▷食欲の「ある」「なし」は、人によって感覚が異なるため、答え方の参考例です。
- いつもと同じ量を完食するのか
- いつもの半分くらい食べるのか
- いつものフードは食べないが、好きなおやつなら食べるのか
- おやつさえ口にしないのか
- 水も飲まないのか 等
このような伝え方をすると、獣医師に伝わりやすいので、是非役立ててください。
④病院または獣医師によって事情が異なるのが、猫ちゃんの保定(猫ちゃんの体を支えること)です。
飼い主さんに委ねる場合と、看護師さんが保定してくれる場合に分かれます。
そこは獣医さんと病院側の方針によるので、行ってから臨機応変に対応しましょう。
体重測定・体温測定・全身チェック

心音や呼吸、毛並み、目・耳・口の状態まで細かく確認されます。
何度か受診すると体重の変化で体調不良に気づくこともあります。
そして触診でわかることはたくさんあります。
※聴診をしている間は、質問等せずに終わるのを待ちましょう。
必要に応じて検査やワクチン

血液検査や便検査、レントゲンやエコー検査、ワクチン接種を必要に応じて行います。
“どうしてその検査が必要か”“費用はどれくらいか”等をきちんと説明してくれる獣医師は安心しますよね。
もし説明がなければ聞いても構いません。
納得した上で診療を進めてもらいましょう。
診察終了・会計・次回予約
診察後は会計し、必要であれば次回のワクチンや健診の予約をします。
診察では“緊張していて聞き忘れた!”がよくあることです。
よくある質問(FAQ)
Q1. 猫を初めて動物病院へ連れて行くとき、絶食は必要?
A. 基本的には不要ですが、受診内容によって異なります。
初診やワクチン、体調相談のみであれば、通常は絶食の必要はありません。
ただし、血液検査や麻酔が必要な検査・処置を行う可能性がある場合は、事前に絶食が必要になることがあります。
初めての受診では、予約時に「絶食が必要かどうか」を事前に確認しておくと安心です。
Q2. 猫が暴れてしまいそうで不安。受診できる?
A. 受診は可能です。多くの動物病院が猫が暴れることを想定して対応しています。
- 洗濯ネット+キャリーで連れて行く
- タオルで包む
- 看護師が保定を行う
など、猫の安全を最優先にした対応を行います。
事前に、
「暴れる可能性がある」
「キャリーから出せないかもしれない」
と伝えておくと、病院側も準備ができ、診察がスムーズになります。
現場で時々あるのが、診察室に入ってすぐにキャリーを開けてしまい、猫が飛び出してしまうケースです。
⚠猫が過敏になっている場合は、キャリーを開けるタイミングは病院スタッフに任せましょう。
そして事前に猫の性格を伝えることで、最低限の接触で刺激を可能な限り減らす工夫ができます。
どうしても診察が難しい場合には、獣医師の判断で、事前にお薬を使って少し落ち着かせてから受診するという選択が取られることも、まれにあります。
Q3. 初めての動物病院はワクチン接種だけでも行って大丈夫?
A. 問題ありません。むしろその目的での初診は多いです。
初診のきっかけとして
- ワクチン接種
- 健康診断
- 爪切り
で来院される方はとても多くいます。
その際、簡単な身体チェックや生活環境の確認が行われ、猫の状態によってはワクチンを見送る判断がされることもあります。
初めての受診だからこそ、
「まずは一度、健康状態を診てもらう」
という目的での来院はとても良い選択です。
まとめ

猫を初めて動物病院に連れて行くのは誰でも多かれ少なかれ緊張するものです。
事前に流れや準備を知っておけば落ち着いて対応できます。
さらに、飼い主さんが気をつけるべきこととして、普段の猫の様子をよく観察し、問診でしっかり伝えられるように準備しておくことが大切です。
そして、飼い主さん以上に緊張するのが猫ちゃんの方です。
通院後は静かな環境で休ませてあげましょう。
準備をして臨めば、飼い主さんの落ち着いた対応が猫ちゃんの安心につながります。
ぜひこの記事を参考に、初めての動物病院を安心して迎えてくださいね。
▼参考リンク(外部サイト)
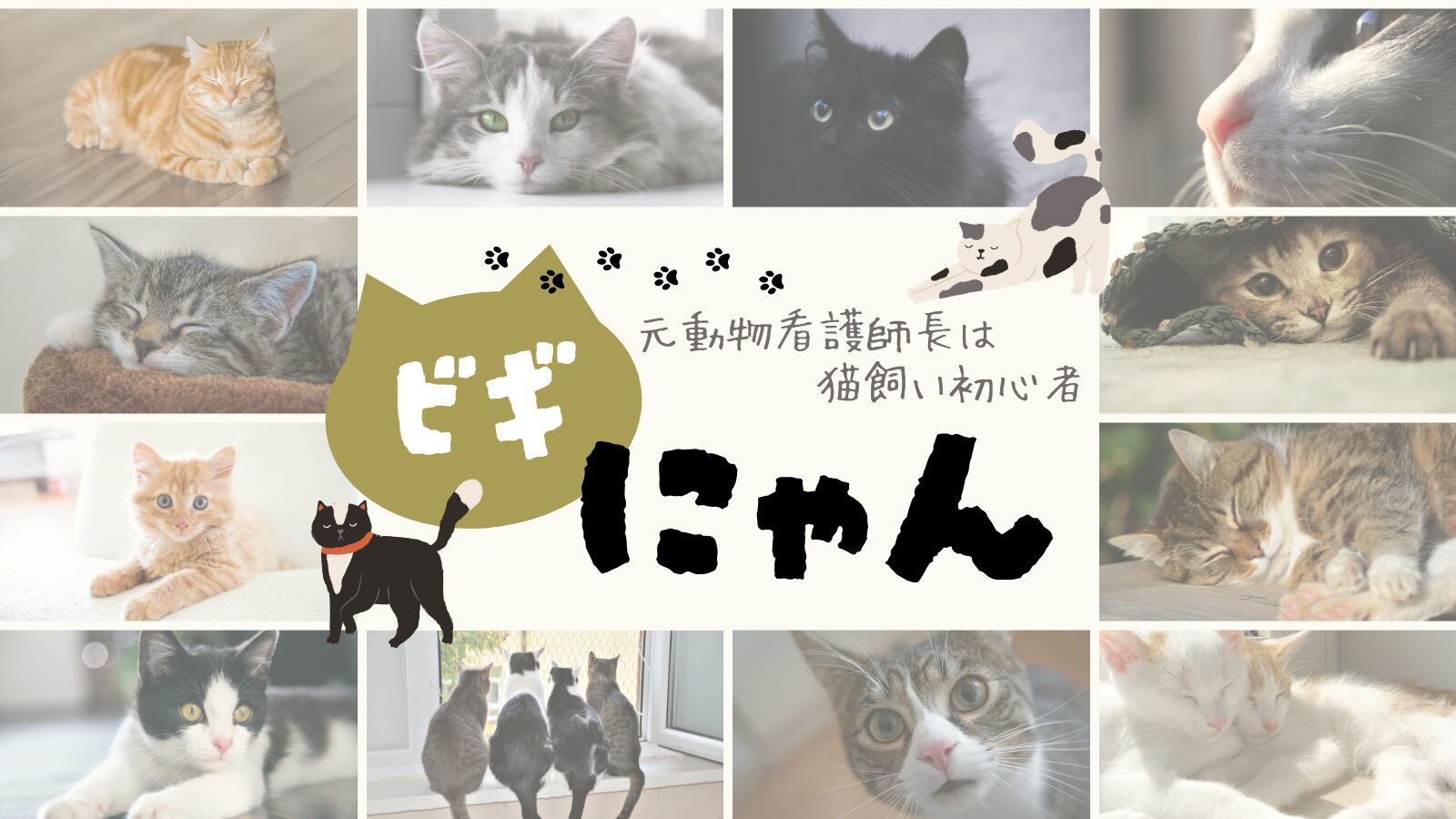
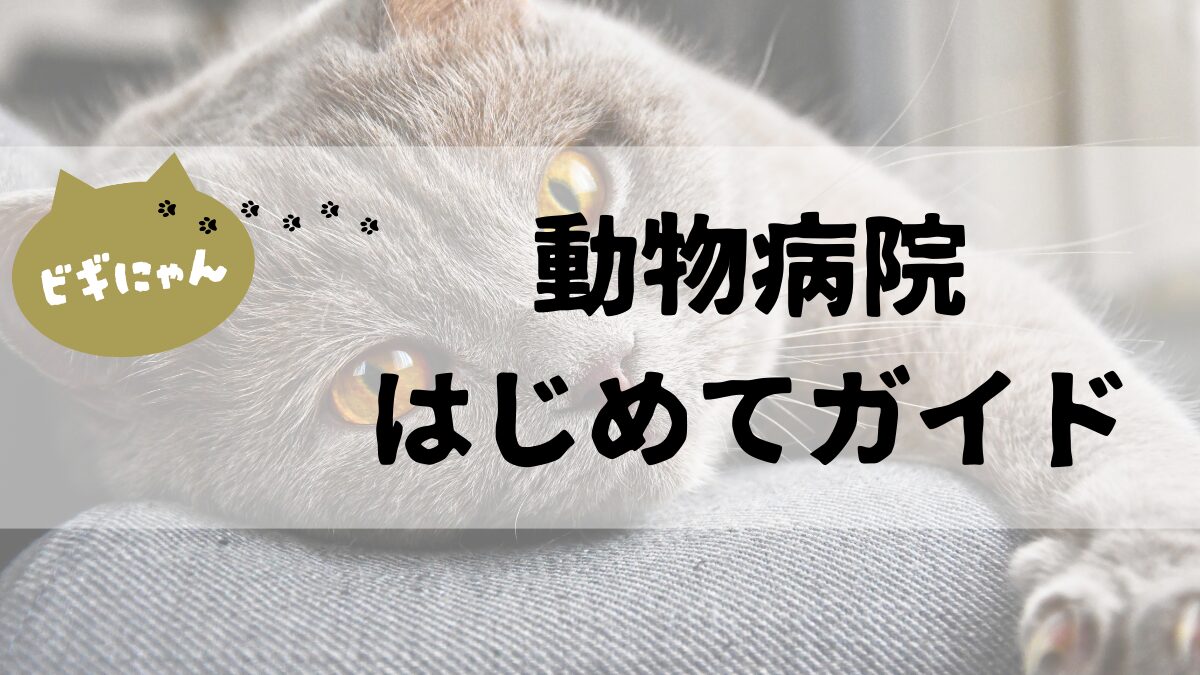


コメント